小説を読もう「死神の精度 伊坂幸太郎」の言葉表現
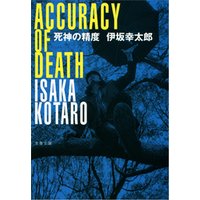
死神の精度 伊坂幸太郎 (著)
頭上の雲は黒々とし、隆々(りゅうりゅう)とした筋肉を思わせる膨らみがある。
雨が垂れていた。激しい勢いではないが、その分、永遠に降り止むこともないような粘り強さを感じさせる。
地下鉄の階段の手前、屋根のある部分に足を踏み入れたところで、私は傘を畳んだ。
「は?」彼女は、いまだかつて耳にしたことのない台詞を聞いた、という顔になる。
「他の人たちは、どこに隠れてるんですか?」彼女の棘のある言い方をした。
彼女がそこで噴き出す。はじめて、彼女の顔にライトが届いたかのように、一瞬ではあるが明るくなった。
職場のビルの前で待ち、自動ドアから出てきた彼女を見つけて、跡を追った。横の車道を車が通り抜け、轍(わだち)に溜まった水を、潮騒のような音を立て、弾いた。
彼女の右肩を叩く。ぴくっと彼女が振り返った。眠っている猫に湯をかけたら、こうなるのではないかと思えるくらい、敏感な反応で、私のほうがたじろいでしまった。
彼女はしばらく黙っていた。何か話すべきだろうか、と思い悩みながら窓の外を見ると、顔をしかめた通行人が傘を差して歩いているのが目に入った。外の歩道にはところどころに水溜まりができていて、地面の凹凸を浮き彫りにしている。
彼女はかなり嫌がっていた。腰を引き、しゃがみ込む寸前というところだ。傘を落としそうでもあった。
その時、藤木一恵が勢い良く、走り出した。しおれた植物のように立っていた彼女は動く気配もなかったのに、突如として逃げたのだ。「あ」と声を上げたのは、私ではなくて、男性のほうだった。
フォームはひどいものだったが、必死さの伝わってくる駆け方だった。手をがむしゃらに振り、頭を傾けて、バッグを落としそうになりながらも走っていく。
気づくと、雨脚が強くなってきたのか、地面に跳ね返る雫が音を立てはじめた。まるで、わたしの結論を、急かすかのようだ。
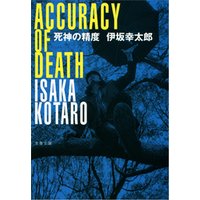
死神の精度 伊坂幸太郎 (著)